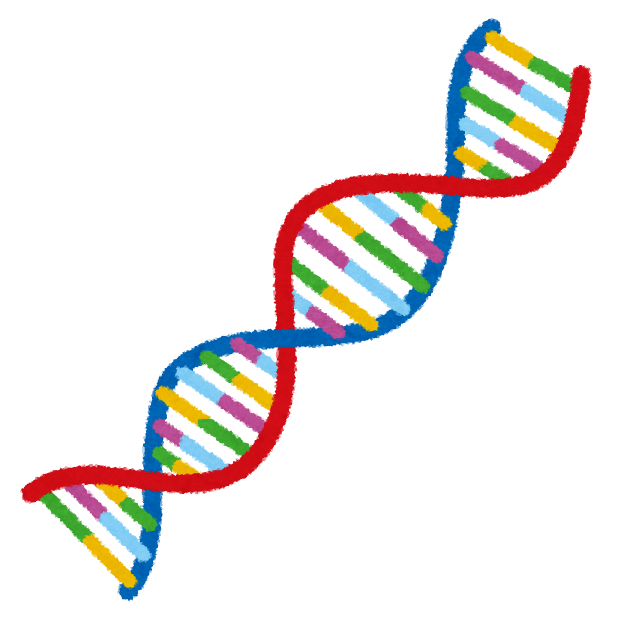CRISPR-Cas9などの遺伝子編集技術は、農作物の改良に革命をもたらす画期的な手法として注目されています。しかし、その一方で、「どう規制すべきか」「消費者にどのように伝えるべきか」という問題が世界中で議論されています。
本記事では、遺伝子組換え(GMO)との違いから、日本・アメリカ・EUの制度の違い、そして今後の課題についてわかりやすく解説します。
1.GMOと遺伝子編集の違いって?
前回の記事「農作物を変える「遺伝子編集」─CRISPR-Cas9の仕組みとその実力」でも述べましたが、簡単におさらいです。混同されがちなのが、「遺伝子組換え(GMO)」と「遺伝子編集(ゲノム編集)」の違いです。
・GMO(遺伝子組換え):他の生物の遺伝子を導入する。例:殺虫性を持つBtコーンなど。
・遺伝子編集:CRISPRなどで、もとの生物の遺伝子を部分的に切ったり書き換えたりする。外来遺伝子が入らないケースも多い。
この違いが、安全性の考え方や規制・表示の仕方に大きく影響しています。
2.日本ではどう扱われているの?
日本では、2019年に厚生労働省と農林水産省が遺伝子編集食品の取り扱い方針を定めました。(令和6年4月から厚生労働省の食品衛生基準行政は消費者庁に移管しています。)
出典1:消費者庁HP 「ゲノム編集技術応用食品の表示に関する情報」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genome/
外来遺伝子が「残っていない」ものは、GMO扱いしない
・安全審査は 不要
・事前の届け出は必須
・食品表示の義務はなし(ただし推奨)
つまり、CRISPRで自然変異と区別がつかないような変化を加えた場合は、従来の品種改良と同じ扱いになります。ただし、表示は義務ではないものの、企業によっては「ゲノム編集食品であること」を自発的にウェブサイトやパッケージで説明しています。透明性を高める取り組みが求められているといえるでしょう。
3.アメリカは原則“規制なし”、表示も自由
アメリカでは、遺伝子編集技術に対して非常に寛容です。
・米国農務省(USDA)は、「外来遺伝子が含まれない限り、規制の対象外」と明言。
・食品医薬品局(FDA)も、義務的な審査を行っていない(ただし、事前相談は可能)。
・食品表示も義務ではない。
出典2:バイテク情報普及会HP
https://cbijapan.com/about_legislation/legislation_w/usa/
その結果、遺伝子編集による耐病性マッシュルームや収穫効率を高めたトウモロコシなどが、すでに販売・栽培されています。
4.EUはGMOと同じ扱いで“厳格に規制”
一方で、EUは最も厳しい対応をしています。
・2018年、欧州司法裁判所は「CRISPRもGMOに該当」との判断を示しました。
・そのため、GMOと同様の承認審査や環境リスク評価が必要。
・食品表示も義務。
このように厳格な規制のため、EU域内では商業的な栽培や流通は進んでいません。
出典3:欧州司法裁判所(ECJ)の大法廷判決
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=851083
5.まとめ
遺伝子編集食品は、規制や表示のあり方によって社会的な受容性が大きく左右されます。
日本では比較的寛容な制度が整っていますが、消費者との信頼構築が不可欠です。
今後の議論では、「規制を緩めるかどうか」だけでなく、いかに誠実に説明し、選択肢を提示できるかが重要になるでしょう。