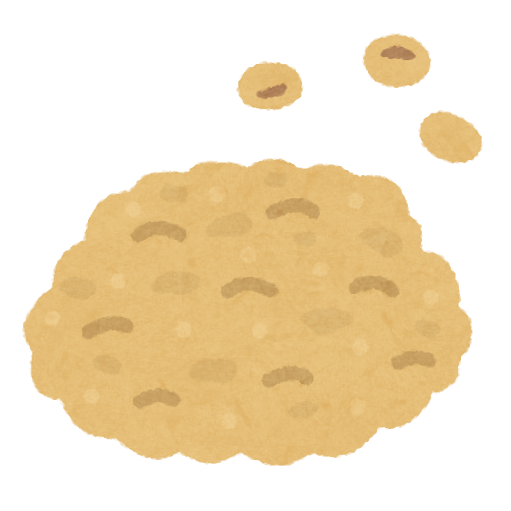近年、食の世界で注目を集めているキーワードの一つが「代替肉」です。
地球環境への配慮、動物福祉、健康志向の高まりといった背景から、植物由来の食材が“未来のタンパク源”として脚光を浴びています。
実は日本には、古くから仏教の精進料理文化があり、「肉を使わずに肉のようなものを作る」技術が受け継がれてきました。例えば、「がんもどき」や「湯葉を巻いた料理」などがその例です。江戸時代には、豆腐を工夫して“鶏肉風”に仕立てる料理もあったとされています。
また、1970年代から80年代にかけては、健康食品ブームやベジタリアン運動が一部で広がり、大豆ミート(ソイミート)は業務用・家庭用の食材として流通していました。
私の実家でも、代替肉は昔から食卓に並ぶお惣菜の一つでした。大豆ミートに甘辛のタレを絡めたおかずは、食欲をそそる味で、今でも記憶に残っています。
そして時代が進んだ今、代替肉は世界的に成長する巨大産業として、改めて注目を集めています。
本記事では、代替肉の基礎知識から、日本国内の代表的プレイヤーである不二製油の最新動向まで、食品技術と業績の両面から読み解いていきます。
1.代替肉とは?種類と技術
代替肉とは、動物の肉の代わりとなる植物性または細胞由来のタンパク源から作られた食品を指します。代表的な分類は以下の通り:
| 種類 | 原料 | 特徴 |
|---|---|---|
| 植物性代替肉 | 大豆、エンドウ豆、小麦など | 市場に多く流通。大豆ミートなどが主流。 |
| 培養肉(細胞培養肉) | 動物細胞を人工的に培養 | 現在は研究段階。将来有望とされるが高コスト。 |
| 発酵肉 | 微生物発酵により生成されたタンパク | 海外で注目が進む。日本では黎明期。 |
2.日本企業の取り組みと展開状況
2-1.伊藤ハム(証券コード:2296):冷凍惣菜型で拡大を加速する総合食品メーカー
伊藤ハム米久ホールディングスは、肉加工品のリーディングカンパニーとして長年親しまれてきましたが、ここ数年は植物性食品の分野にも積極的に進出しています。中でも注目されているのが「まるでお肉!」シリーズです。
出典1:伊藤ハム公式HP
https://www.itoham.co.jp/product/product/serieslist.html?catid=248
このシリーズは、大豆などの植物性たん白を主原料に、まるで本物の肉のような食感・風味を実現した冷凍食品で、ハンバーグ、メンチカツ、からあげ、ナゲットなどの幅広いラインナップが展開されています。特徴的なのは、“冷凍惣菜”という形態を活かし、家庭でも手軽に調理できる利便性と、惣菜売り場でも扱いやすい商品性を両立している点です。
2-2.大塚食品:ZERO MEATで飲食チェーン・家庭の両方へアプローチ
医療・ヘルスケア関連で知られる大塚グループの一員である大塚食品も、植物性食品市場において存在感を高めています。同社の代替肉ブランド「ZERO MEAT(ゼロミート)」は、動物性原料やコレステロールを一切使用せず、植物性原料だけで構成されたハンバーグやソーセージなどの加工食品を展開しています。
出典2:大塚食品公式HP
https://zeromeat.jp/
ZERO MEATの特長は、味の再現度の高さと、食べごたえのある食感です。植物性でありながら肉のようなジューシーさを感じさせる工夫が施されており、ベジタリアンやヴィーガンはもちろん、健康志向の高い一般消費者からも支持を集めています。
2-3.マルコメ:乾燥タイプで家庭需要をつかむ“和風ソイミート”の先駆者
味噌や発酵食品で知られるマルコメは、「ダイズラボ」ブランドを通じて、乾燥大豆ミート(大豆のお肉)の家庭用商品化に早くから取り組んできた企業です。ブロックタイプやミンチタイプなど、さまざまな形状で展開されており、湯戻しして調理することで、炒め物やカレー、煮物などに幅広く活用できます。
出典3:マルコメ公式HP
https://www.marukome.co.jp/daizu_labo/
マルコメの大豆のお肉は、味噌などで培った大豆加工技術を活かし、和食にも合う風味と食感を追求しているのが特徴です。保存性の高さや価格の手頃さもあり、「家庭で手軽に代替肉を取り入れたい」という層に支持されています。
また、乾燥タイプは常温保存が可能なことから、非常時の備蓄食材や、長期ストック食品としても注目されており、店舗だけでなくECサイトや生協などでも取り扱いが増えています。
3.大豆肉関連の老舗メーカー「不二製油(証券コード:2607)」、代替肉分野での静かな苦戦
不二製油の株価情報(Investing.com)不二製油グループは、植物性食品素材のパイオニアとして、日本だけでなく世界的にも高く評価されている企業です。なかでも大豆タンパクの加工技術においては、1957年から研究を続けており、業務用の粒状大豆ミート(TVP*)においては、国内シェア約50%を占める圧倒的な供給力を持っています。
*TVP(Textured Vegetable Protein)は、不二製油が製造・販売している大豆を主原料とした組織状植物性たん白のことです。肉のような食感を再現できるため、代替肉や加工食品の原料として幅広く利用されています。
そのため、私たちが日常的に食べている冷凍食品や外食メニューの裏側では、不二製油の技術が支えているケースも少なくありません。自社ブランドで表に出ることは少ないものの、食品メーカーや外食産業に向けた“素材インフラ”としての役割を担っているのが同社の大きな特徴です。
参考:特許第5794373号
特許情報プラットフォーム https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-5794373/15/ja
従来の大豆ミートは価格面や加工性に優れる一方で、リアルな肉のような食感には限界がありました。本特許では、所定量のオート麦ファイバー(オーツ麦の外皮から水溶性成分を除いた不溶性繊維)を加え、更に繊維の長さを最適化する等して、この課題を解決しています。
技術解説
(1)技術面での三本柱
Prime Soy Meat(プライムソイミート)
従来の大豆ミートは「ボソボソした食感」や「独特の匂い」が課題とされてきましたが、Prime Soy Meatでは、繊維感・弾力・舌触りなどに細やかな改良が加えられ、本物の肉に近い“食感のリアルさ”を追求しています。製品によって粒のサイズや質感を調整できる点が、業務用としても重宝されています。
出典4:不二製油公式HP プライムソイ
https://www.fujioil.co.jp/product/soy/primesoy/
(2)MIRACORE技術
植物性の食材では再現が難しいとされてきた「ジューシーさ」や「肉汁のような口あたり」を、植物性油脂とタンパク質の複合技術で表現可能にしたのがMIRACORE。この技術によって、代替肉の“物足りなさ”を補い、より満足感のある食事体験を提供できます。
出典5:不二製油公式HP ミラコア
https://www.miracore.jp/
(3)MIRA-Dashi(ミラだし)
さらに注目されているのが、「だし」の分野。動物性原料を使わずに、鶏がらや魚介のような出汁の風味を再現した「MIRA-Dashi」シリーズは、ヴィーガンや宗教上の理由で動物性を避ける人々にとって重要な選択肢となっています。チキン風、ビーフ風、豚骨風、かつお風味など、バリエーションも豊富です。
出典6:不二製油公式HP ミラだし
https://mira-dashi.com/
4.苦戦する現状とその背景
このように、技術面では業界を牽引する不二製油ですが、業績面では近年やや苦戦が続いているのも事実です。
・2025年3月期は売上こそ前年比+19%と大幅増でしたが、営業利益率は1.5%、ROEも1.01%と、収益性の低さが目立ちます。
・原料高騰・物流費・人件費などのコスト増に加え、植物性食品分野における価格競争や需要鈍化が足を引っ張っています。
・また、企業としては長期的視点で「サステナブル食品素材」の地位を確立しようとしていますが、目先の利益と投資のバランスに苦労している状況です。
出典7:不二製油公式HP 有価証券報告書 2024年度
https://www.fujioil.co.jp/pdf/ir/library/negotiable/97th_full.pdf
5.今後の展望
とはいえ、不二製油は日本国内にとどまらず、シンガポール、オランダ、アメリカなど世界各地に研究・生産拠点を展開し、グローバルな視点で植物性食品の技術開発を加速させています。さらに、2030年には植物性食品関連事業で年間1,000億円規模の売上を目指すという中長期戦略も掲げており、その姿勢には大きな成長意欲が感じられます。
プラントベース市場が世界的に拡大する中で、不二製油がどのように存在感を高めていくのか—その一手一手から目が離せません。
※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄や金融商品の購入・売却を勧誘するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。また、本記事の内容によって生じたいかなる損失についても、当サイトでは一切の責任を負いかねます。