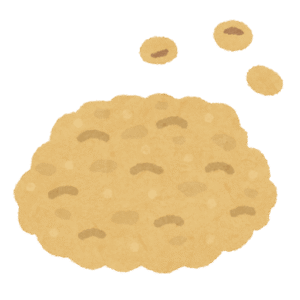こんにちは。
景気変動に振り回されにくい銘柄を探している方にとって、「ディフェンシブセクター」は有力な選択肢です。中でも、食料品をはじめとした生活必需品関連銘柄は、安定した業績と配当が魅力です。
本記事では、そんなディフェンシブセクターのメリット・デメリットを整理し、具体的な日本株・米国株の代表銘柄を交えて詳しく解説します。
1.景気は波のように変動する ―「景気循環理論」の基本
私たちの経済は、常に一定ではなく、好調な時期と不調な時期を繰り返すサイクルの中にあります。これを「景気循環(ビジネスサイクル)」と呼びます。
一般的に、景気は以下の4つの局面を順番に進んでいくとされています:
・回復期(Recession to Recovery) 経済が底を打ち、雇用や消費が徐々に改善し始める時期
・拡張期(Expansion) 企業業績や株価が伸び、経済が最も活発になる好景気の時期
・後退期(Slowdown) インフレや金利上昇の影響で、経済成長が鈍化し始める時期
・不況期(Recession) 企業の業績が悪化し、失業率が上昇する景気の底
このように景気が波のように上下する中で、どの業種の株が買われるかも変わってくる、というのが「景気循環理論」の考え方です。
2.ディフェンシブセクターとは?
ディフェンシブ(defensive)セクターとは、上記の後退期~不況期においても、景気の影響を受けにくく、安定した業績が期待できる業種を指します。主な業種には以下のようなものがあります:
・食料品/飲料
・医薬品
・生活用品
・公共事業(電力・ガス・水道)
これらの企業は、人々の「日常生活に欠かせない」商品やサービスを提供しているため、不況時でも需要が大きく落ち込みにくいという特徴があります。
【ディフェンシブETFの代表例、XLPのチャート】
補足:高金利との関係は?
なお、食料品を含むディフェンシブ銘柄は、高金利下でも需要が大きく落ちにくいという特徴があります。ただし、借入コストや原材料費の上昇といった圧力もあり、「高金利に強い」とまでは言い切れません。ボラティリティの大きいグロース株に比べれば耐性がある、という程度に捉えておくとよいでしょう。
3.メリット/デメリットについて
メリット① (景気)後退時にも強い
不況期にも一定の需要があり、業績が安定しやすいのが最大の強みです。
例えば、
・日清食品HD(2897)
カップ麺やインスタント食品を手がける同社は、景気の影響を受けにくい典型例。コロナ禍でも売上が堅調で、株価も比較的安定して推移しました。
出典1:【2021年1月5日】東洋経済オンライン「日清食品、巣ごもり需要で業績上方修正」
https://shikiho.toyokeizai.net/news/0/401605?utm_source=chatgpt.com
メリット② 株価が安定し、長期保有に向いている
成長株のように急騰することは少ないですが、その分値動きが穏やかで、ポートフォリオの「守り」の役割を果たしてくれます。
例えば、
・キッコーマン(2801)
醤油をはじめとする調味料で海外展開も進めており、業績は安定。ボラティリティが低く、長期的にじわじわ成長している点も魅力です。
出典2:キッコーマン公式サイト「Overseas expansion」
https://www.kikkoman.com/en/corporate/history/outline/?utm_source=chatgpt.com
メリット③ 高配当銘柄が多く、インカムゲインに最適
安定したキャッシュフローを背景に、株主還元に積極的な企業が多いのもディフェンシブ銘柄の特徴です。
例えば、
・Kraft Heinz(KHC)
米国大手食品メーカー。業績は成熟気味ですが、配当利回りは6%前後(2025年6月現在)と高水準を維持。配当重視の投資家に人気です。
出典3:NASDAQ上の配当履歴情報
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/khc/dividend-history?utm_source=chatgpt.com
デメリット① 好況時には出遅れやすい
景気拡大局面では、テクノロジーや金融などのシクリカルセクターに注目が集まり、ディフェンシブ銘柄は相対的にパフォーマンスが劣る傾向があります。
例えば、
・Procter & Gamble(PG)
堅実な企業である一方、ITバブル期や景気拡大局面ではハイテクセクターにパフォーマンスで負けることもしばしば。
出典4:「Are Wall Street Analysts Predicting Procter & Gamble Stock Will Climb or Sink?」
https://www.nasdaq.com/articles/are-wall-street-analysts-predicting-procter-gamble-stock-will-climb-or-sink?utm_source=chatgpt.com
デメリット② 人気化しすぎて割高になることも
「安全資産」として買われるあまり、業績に比べて株価が高くなってしまうケースもあります。
例えば、
・ライオン(4912)
衛生用品の需要増で注目されましたが、PERが過熱気味になり、成長鈍化局面では株価が下落するリスクも。
出典5:「ライオン株式会社(東証:4912)の投資家人気は、割高感から脅かされている」
https://simplywall.st/ja/stocks/jp/household/tse-4912/lion-shares/news/525498f358932356?utm_source=chatgpt.com
4.相場環境によって「守りと攻め」を使い分けよう
ディフェンシブセクターは、相場全体が不安定なときほど価値を発揮する「守りの資産」です。特に食料品関連は生活に不可欠であり、不況耐性が高いのが魅力。
ただし、常に市場平均を上回るとは限らず、資産の一部に組み入れる「バランサー」として活用するのが現実的です。セクターサイクルや相場の温度感を見ながら、攻め(グロース株)と守り(ディフェンシブ)のバランスを調整していきましょう。
最後に、食料品銘柄と特許との関係は投資家にあまり意識されにくい側面がありますが、特許による製法の独自性や品質向上技術は、長期的にブランド力や収益力の源泉となることがあります。
例えば、保存性・風味の改良、植物由来成分の抽出技術などの特許は、競合との差別化やプレミアム価格の維持につながることがあります。こうした特許による「見えない競争力」は、ディフェンシブ銘柄としての株価安定性を裏から支える存在と言えるでしょう。
※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄や金融商品の購入・売却を勧誘するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。また、本記事の内容によって生じたいかなる損失についても、当サイトでは一切の責任を負いかねます。