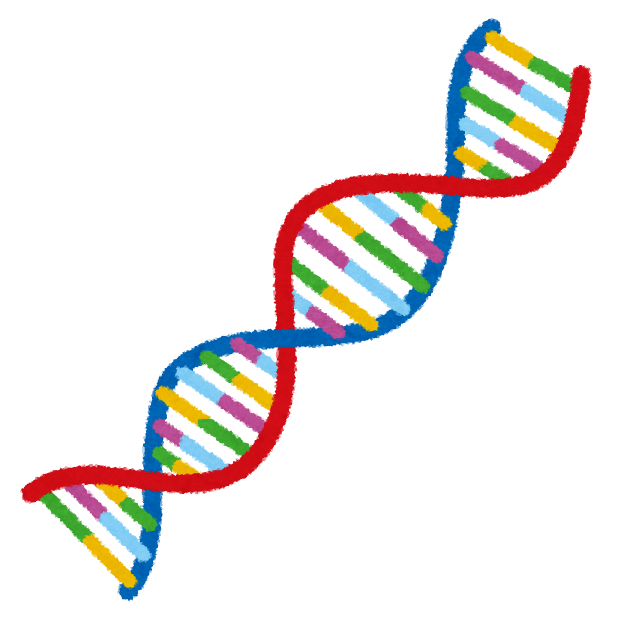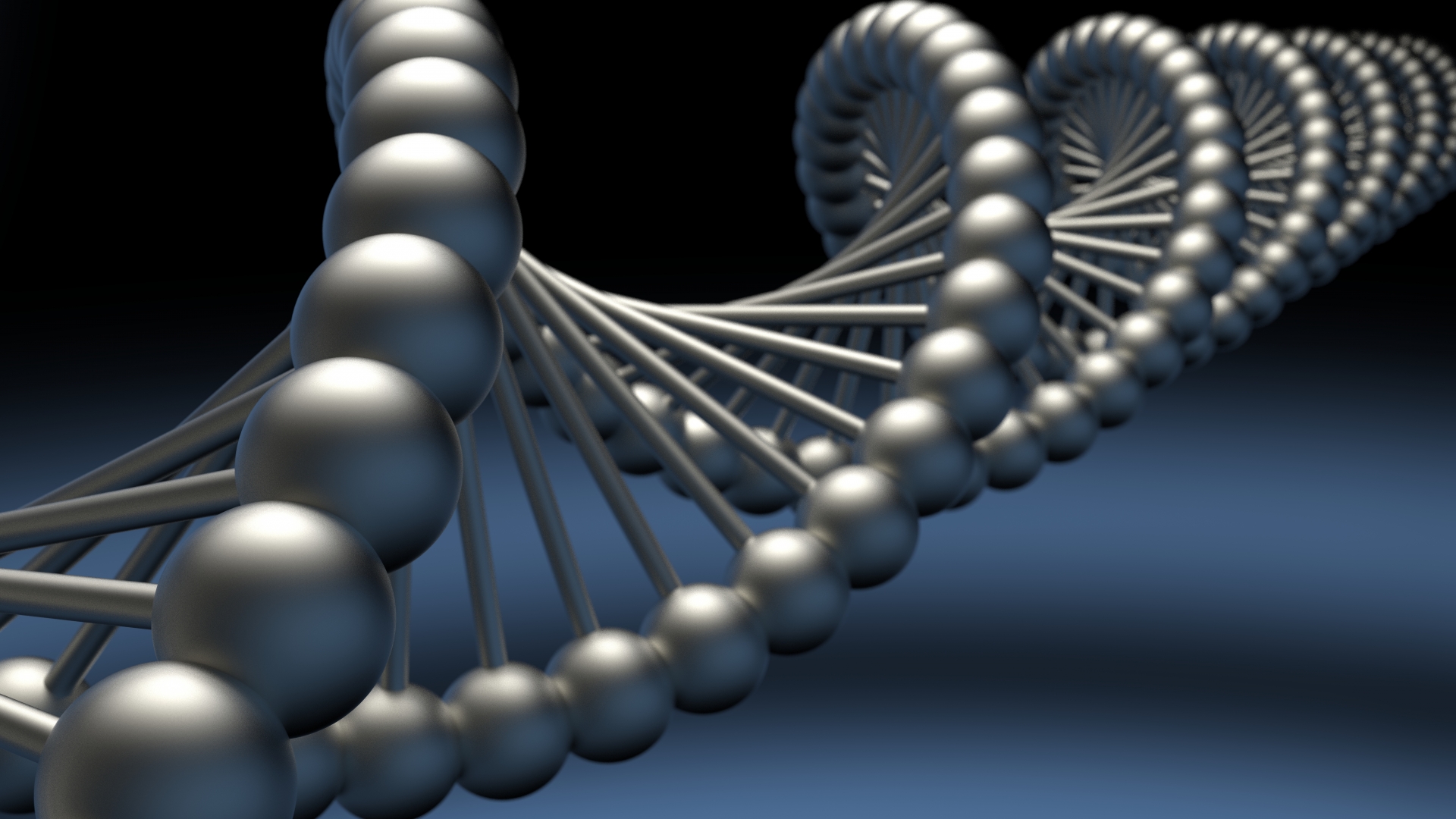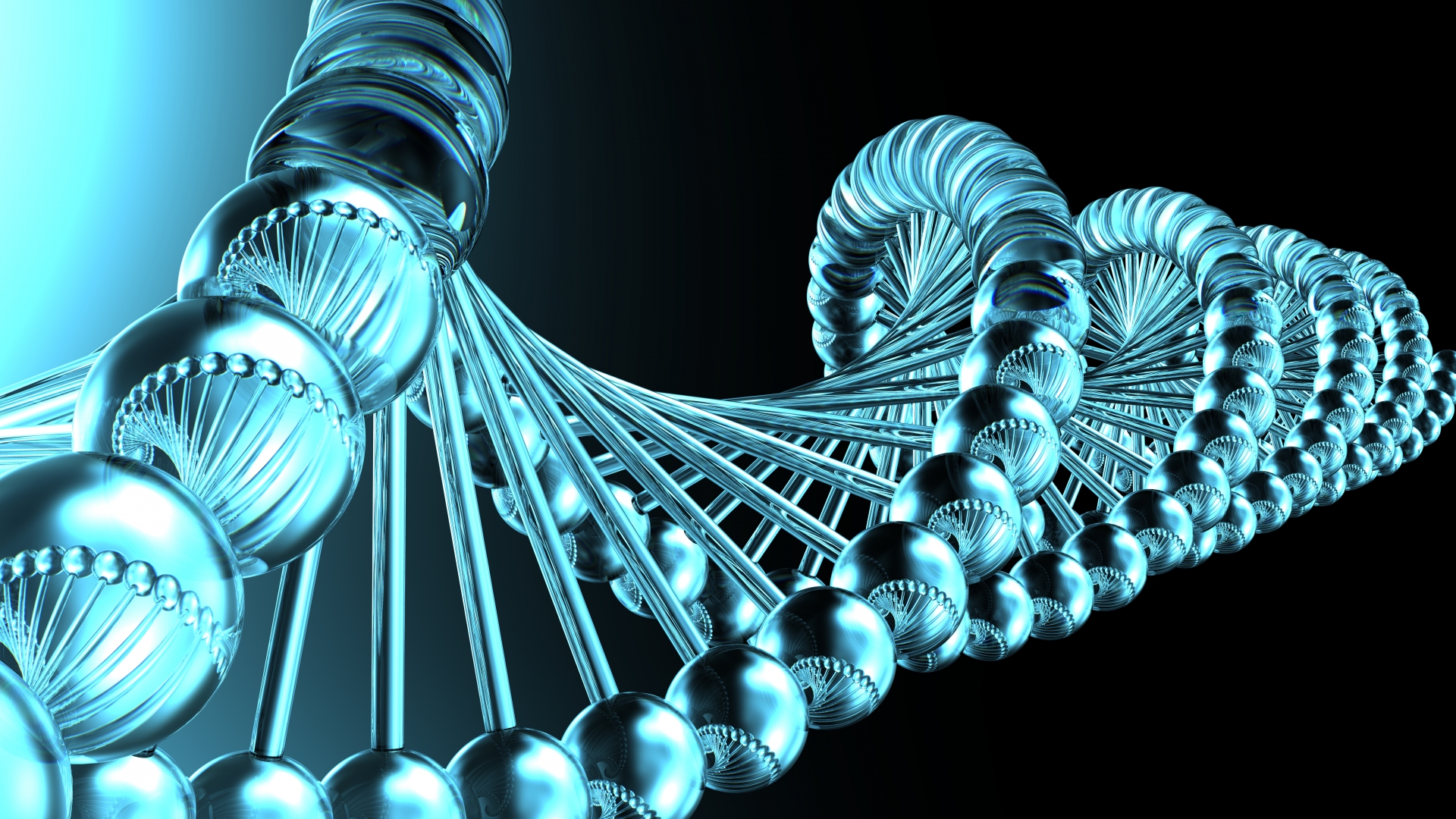本記事は、CRISPR/Cas9特許を巡る知財高裁判決を解説する全3部シリーズの第1回です。
2025年6月26日、知的財産高等裁判所は、ゲノム編集技術「CRISPR/Cas9」に関する日本の重要な特許紛争で判決を下しました。
原告はツールゲン社、被告(=特許権者)はカリフォルニア大学・ウィーン大学・発明者チーム(うちノーベル賞受賞者を含む)です。今回の判決は、国際的に続く「CRISPR特許戦争」の一環であり、日本でも大きな注目を集めました。
1.争点は「優先権」
問題となったのは、特許第6692856号(CRISPR/Cas9システムに関する特許)の優先日が 2012年5月25日 に遡れるかどうか、という点でした。
もし優先日が認められれば、同年後半に出願された競合特許はすべて「後発」となります。逆に認められなければ、本特許は無効になる可能性がありました。
時系列:
①2012年5月25日
米国仮特許出願の第61/652,086号を基礎出願として行う
②2013年3月15日
上記①を含む4件の優先権を主張して本件出願 → 2020年3月24日 特許査定(特許第6692856号)
③異議申立・無効審判を経て、審決取消訴訟が提起され、2025年6月26日に判決。
出典1:特許情報プラットフォーム 特許第6692856号
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2018-097369/10/ja
【補足】優先権制度とは
優先権制度は、特許出願日という「先着順の権利」を確保するための仕組みです。
1883年のパリ条約で国際的に導入され、日本は1899年に加盟しました。
例えば、A国で最初に特許出願aを行い、一定期間内にB国(または同じA国)で特許出願bを行った場合に、出願人が優先権を主張すれば、aとbで共通する発明部分については、最初の出願日(aの日付)を基準に扱うことができます。
今回の裁判では、この「共通する発明部分」が CRISPR/Cas9の真核細胞への適用 にあたるかどうかが争点となりました。
【補足】CRISPR/Cas9システムと真核細胞
・CRISPR/Cas9システム:ガイドRNAで標的DNAを認識し、Cas9酵素で切断して遺伝子を編集する技術。
詳しくは「農作物を変える「遺伝子編集」─CRISPR-Cas9の仕組みとその実力【遺伝子編集②】」
・真核細胞:核を核膜で囲む構造を持つ細胞(例:動物細胞)。一方、細菌細胞は核膜がなく、核は細胞質中に浮遊して存在します。
原告(ツールゲン社)の主張
・第1出願(2012年5月25日)には真核細胞での実施例や具体的適用方法が記載されていない
・当時、ヒト細胞での成功例はなく、適用には過度の試行錯誤が必要
・PAM配列、NLS、コドン最適化など重要要素も明示されていない
第1出願は、試験管内(in vitro)および細菌細胞での動作は実証していたものの、真核細胞での実証は示していません。
細菌細胞と真核細胞では核構造が異なるため、核への到達には追加の技術的課題があります。例えば、CRISPR/Cas9 が DNA に作用するためには、まず核膜を通過して核内のDNAにアクセスする必要があります。原告はこのことを争点にしました。
被告(カリフォルニア大学ら)の反論
・第1出願全体の記載と当時の技術常識から見れば、真核細胞への適用は当業者にとって実施可能
・PAM配列・NLS・コドン最適化は2012年時点で周知技術
・ZFN や TALEN では既に哺乳類細胞のゲノム編集が確立しており、発現ベクターやトランスフェクションも慣用手段だったため、過度な試行錯誤は不要
2.知財高裁の判断
裁判所は被告の主張を支持し、優先日を2012年5月25日と認めました。
判決の要点:
2-1.優先権の解釈
判断は請求項だけでなく出願書類全体と当時の技術常識を総合し、「当業者が過度の試行錯誤なく実施できるか」で行うべき
2-2.第1出願の開示
Cas9とDNA標的化RNAによる複合体、PAM依存的切断の原理、NLSやコドン最適化の可能性を開示し、真核細胞の染色体も対象に含むと明記
2-3.技術的背景の重視
ZFN/TALENやトランスフェクション、発現ベクターは当時の慣用技術であり、それらをCRISPR/Cas9に応用することは自然な発想
3.判決の意義
この判決は、「実験成功の有無」ではなく「実施可能性と技術常識」に基づき優先権の範囲を判断した点で重要です。
ライフサイエンス分野の特許実務では、具体的データがなくても、全体の開示と当時の知識を踏まえれば実施可能と認められる場合があることを示しました。
特に、
・PAM配列・NLS・コドン最適化が2012年時点で「当たり前の技術」と評価されたこと
・ZFN/TALENで築かれた真核細胞編集の基盤がCRISPR/Cas9の優先権を支えたこと
は技術史的にも注目されます。
出典2:知財高裁HP 令和5年(行ケ)第10147号 審決取消請求事件
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/094292_hanrei.pdf
参考:Martin Jinek et al., Science (2012年6月掲載)“A Programmable Dual‑RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity”
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1225829
*この論文は Doudna 氏と Charpentier 氏らの共著であり、2020年のノーベル化学賞が両者に共同授与されています
次回予告
第2部では、この判決のキーワードである「PAM配列」「核局在化シグナル(NLS)」「コドン最適化」について、判決文からは見えにくい“技術的な裏側”を解説します。