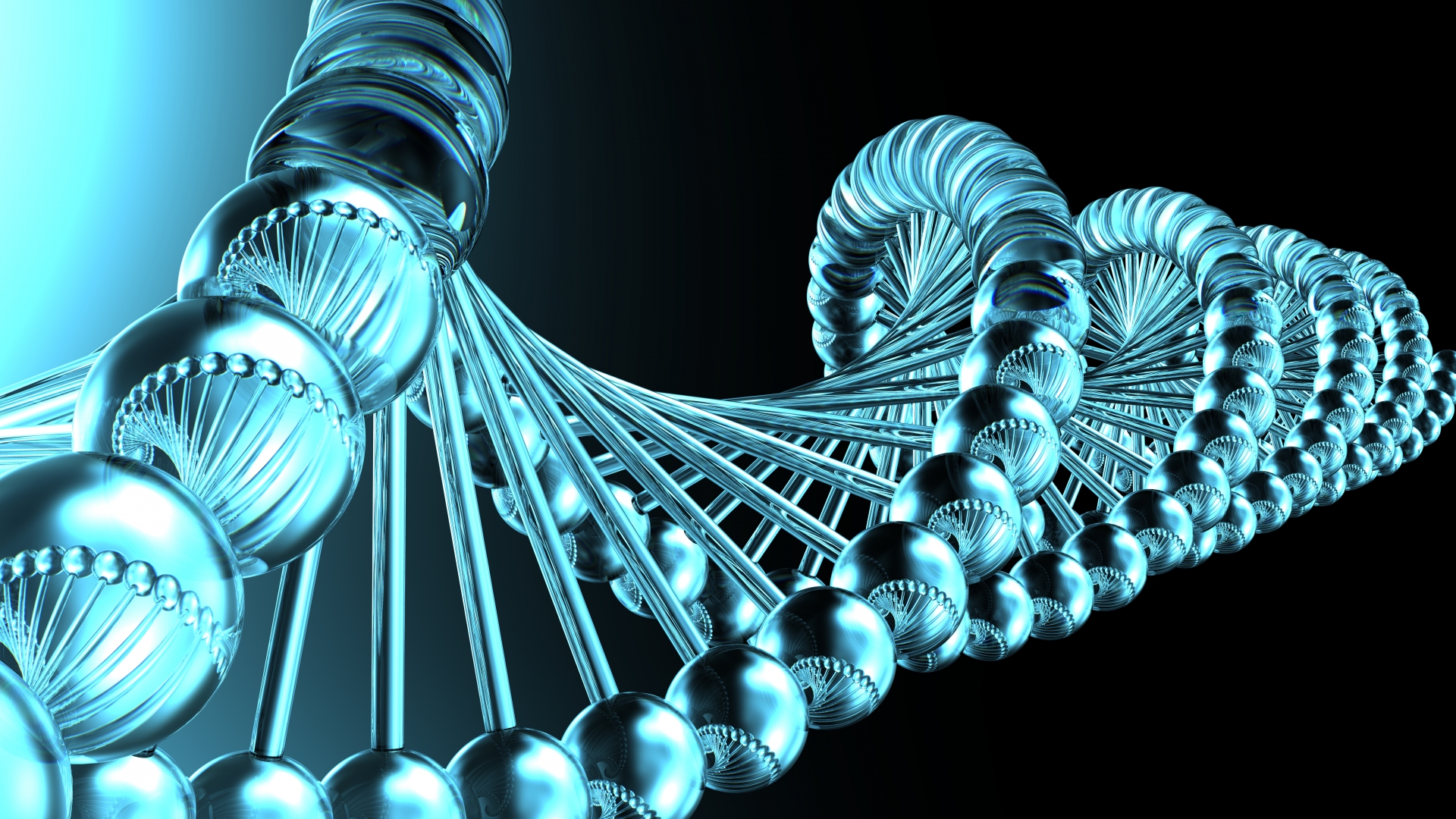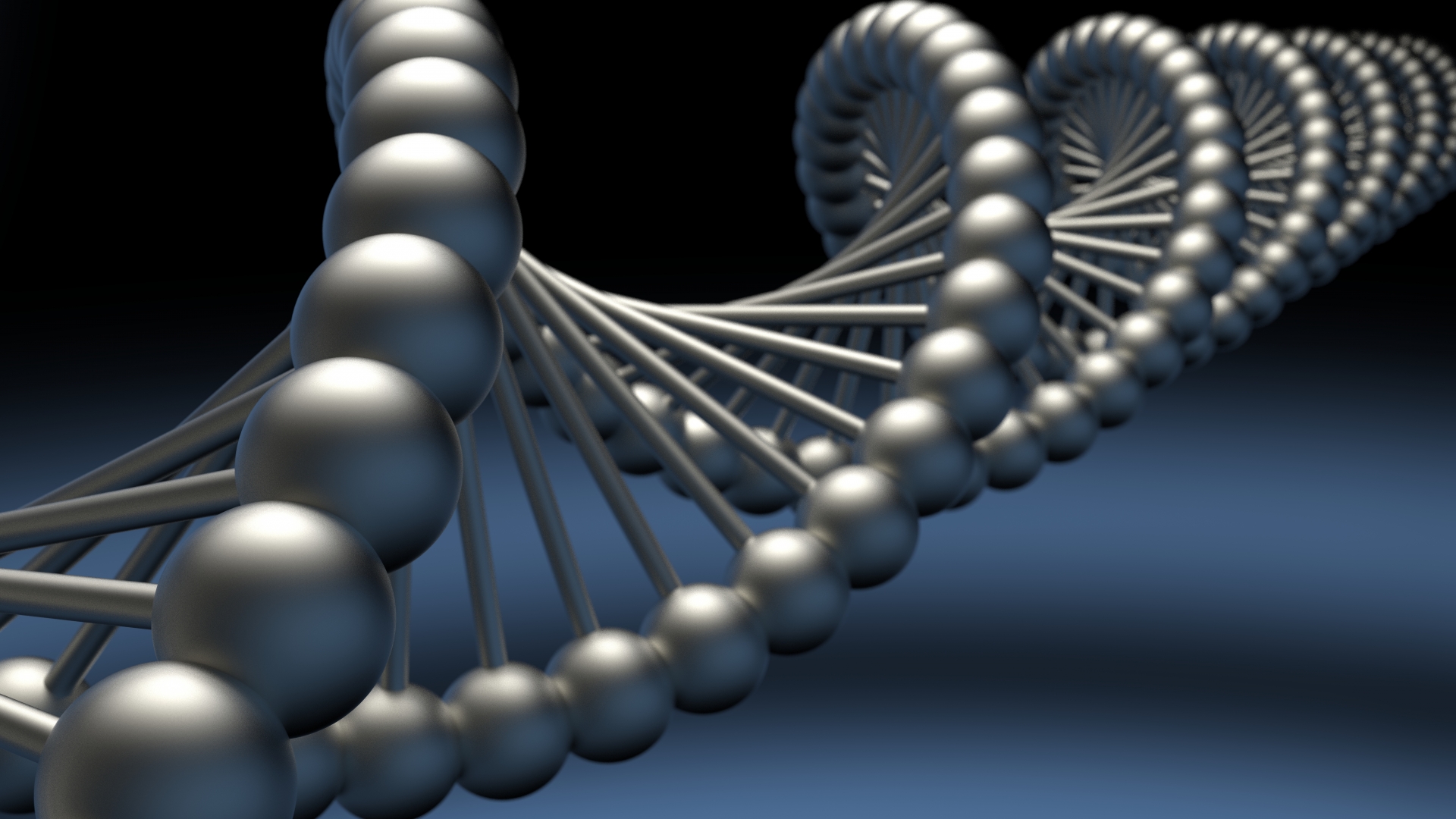本記事はCRISPR/Cas9特許を巡る知財高裁判決を解説する全3部シリーズの第3回です。
CRISPR/Cas9は「ゲノム編集の革命」と言われますが、その成功はゼロから生まれたものではありません。今回の知財高裁判決でも重視されたのは、2012年当時すでに存在していたゲノム編集の基盤技術です。特に、ZFNやTALENといった先行ツール、そしてそれらを支えたトランスフェクションや発現ベクターの存在は、優先権の判断で大きな意味を持ちました。
1.ZFN(ジンクフィンガーヌクレアーゼ)
ZFNは、DNAに結合するジンクフィンガードメインと、DNAを切断するFokIエンドヌクレアーゼを組み合わせた人工酵素です。
・1つのジンクフィンガーは3塩基を認識し、複数を並べることで特定のDNA配列を狙えます。
・2つのZFNが標的DNAの両側に結合すると、FokIが二本鎖を切断し、細胞の修復機構を利用して遺伝子改変を行います。
2000年代後半、ZFNは哺乳類細胞やゼブラフィッシュ、植物でのゲノム編集に利用され、論文・特許が多数公開されていました。2012年時点で「真核細胞の遺伝子を人工的に切る」ための実績は十分に存在していたのです。
2.TALEN(転写活性化因子様エフェクターヌクレアーゼ)
TALENは植物病原菌由来のDNA結合タンパク質(TALE)を利用したツールで、DNA配列を1塩基単位で認識できるのが特徴です。
・TALEとFokIを融合させることで、標的部位を自由に設定できます。
・ZFNに比べ設計が容易で、2011年頃から急速に普及しました。
TALENはヒト細胞やマウス胚での実験も進んでおり、CRISPR/Cas9登場前夜には「次世代の編集ツール」と呼ばれていました。知財高裁は、このTALENの存在が「真核細胞での標的編集は当業者にとって可能だった」ことを裏付けるものと評価しています。
参考:ファルマシア 2015 年 51 巻 4 号 p. 305-309「次世代の遺伝子改変技術としてのゲノム編集」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/faruawpsj/51/4/51_305/_article/-char/ja/
*ZFN、TALEN、CRISPR/Cas9の構造的な違いを模式図入りで分かりやすく表現しています。
3.発現ベクターとトランスフェクション
ZFNやTALENの実験では、外来遺伝子を細胞に導入して発現させるための発現ベクターと、DNAやRNAを細胞内に運ぶトランスフェクションが欠かせません。
・発現ベクターは、目的の遺伝子を細胞に届けて機能させる「運搬装置」です。プロモーターやエンハンサー、選択マーカーを組み込み、外来遺伝子が細胞内で効率よく働くよう設計されています。
・トランスフェクションはDNA/RNAを細胞に導入する技術の総称で、リポフェクション、エレクトロポレーション、ウイルスベクターなど複数の手法が使われます。
2012年時点でこれらの技術はすでに標準化されており、「外来の編集ツールを哺乳類細胞で働かせる」ためのプロトコルは確立していました。裁判所は、CRISPR/Cas9もこの枠組みを利用するだけであり、CRISPR/Cas9システムの概念があれば、真核細胞への適用が、「特別な試行錯誤を必要としない」と判断しました。
4.CRISPR/Cas9は「突然の革命」ではなかった
判決の裏側から見えてくるのは、CRISPR/Cas9が「技術史の延長線上にあった」という事実です。ZFNやTALENで培われた標的編集の概念、真核細胞での遺伝子導入と発現技術、PAMやNLS、コドン最適化といった分子生物学の慣用技術―これらが揃っていたからこそ、「当業者が真核細胞で実施可能」であり「優先権主張の利益は享受できる」と裁判所は判断しました。
この点は特許実務においても重要です。ライフサイエンス分野では、実験データがなくても「全体の開示+当時の技術常識」で実施可能とされる場合があることを今回の判決は示しました。
5.技術と法務の交差点
CRISPR/Cas9はノーベル賞級の発明でありながら、その権利範囲は既存技術との関係で決まります。今回の知財高裁判決は、単なる「発明の優劣」ではなく、科学と法の両面からゲノム編集技術の進化を映し出した事例と言えるでしょう。