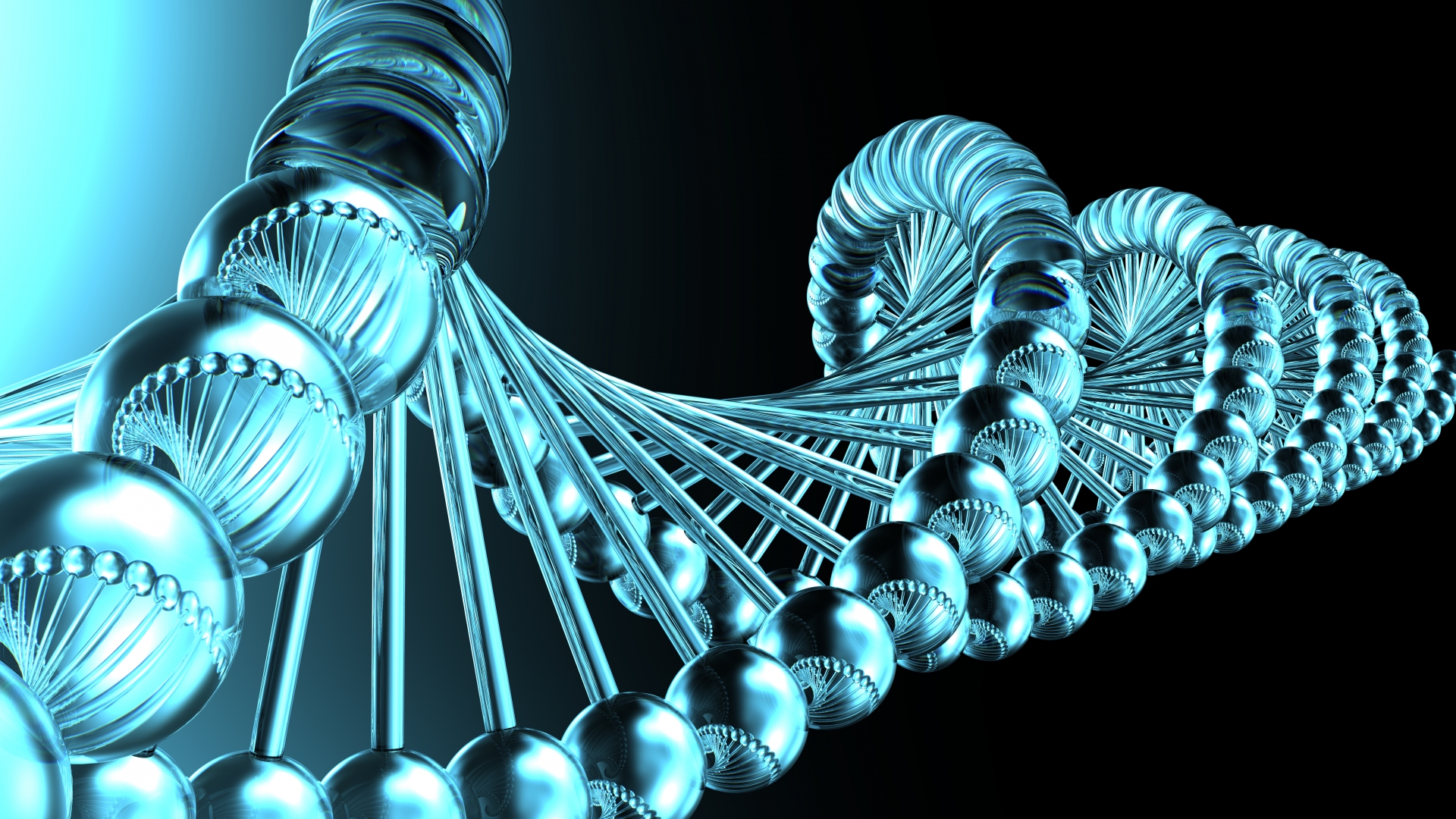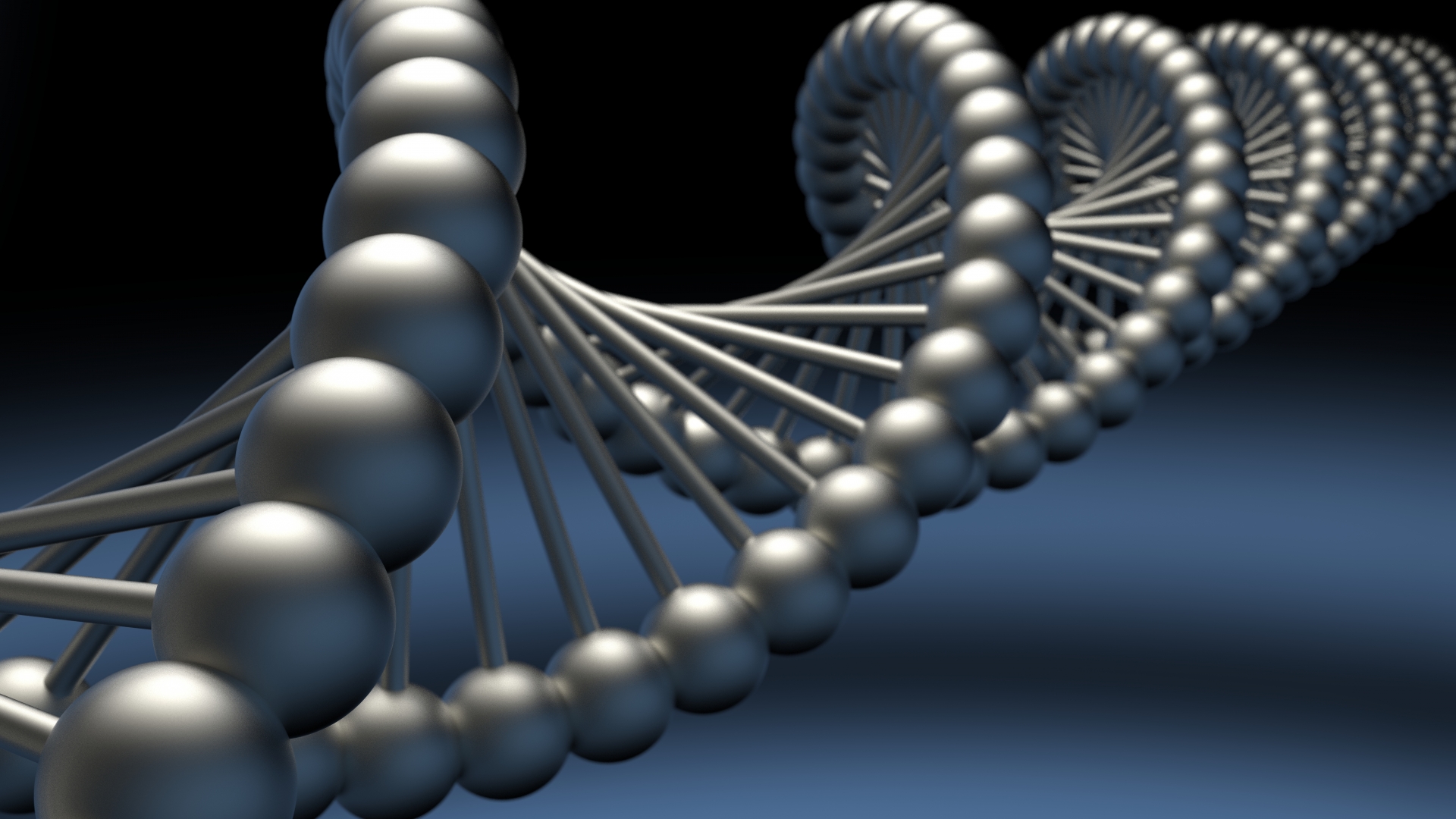本記事はCRISPR/Cas9特許を巡る知財高裁判決を解説する全3部シリーズの第2回です。
CRISPR/Cas9特許の知財高裁判決では、「2012年当時すでに知られていた技術」が優先権判断の大きな鍵となりました。特に重要視されたのが、プロトスペーサー隣接モチーフ(PAM)、核局在化シグナル(NLS)、そしてコドン最適化という3つの要素です。ここでは、それぞれの技術を整理してみましょう。
1.プロトスペーサー隣接モチーフ(PAM配列)
CRISPR/Cas9は、Cas9タンパク質とガイドRNA(crRNA+tracrRNA)からなる複合体が標的DNAを探し出して切断する仕組みです。しかし「どこでも切れる」わけではありません。標的配列のすぐ隣にPAM(protospacer adjacent motif)と呼ばれる短い配列が存在する必要があります。
元来、CRISPR/Cas9システムを備える細菌は、ウイルスの攻撃を受ける際に、PAM配列によって「自己」DNAと「非自己」DNAを区別しています。細菌細胞自身のDNAにはPAM配列がないため、Cas9は細菌自身のDNAを攻撃することはありません。しかし、侵入してきたウイルスはPAM配列を持っているため、Cas9の分子ハサミの標的となります。これは、味方への誤射を防ぐ安全装置のような機構です。
原告は、最初の基礎出願には真核細胞に関する実施例がないのだから、PAMが真核細胞でも必要な存在であることは当時明らかでなかったはずだ(だから優先権の適用範囲外だ)と主張していました。
しかし、2011年の時点で、複数のレビュー論文や実験結果により「PAMがなければ切断が起こらない」ことはすでに確認されていました。そのため、判決では「2012年時点でPAM配列の重要性は分子生物学分野の技術常識」と認定されました。
2.核局在化シグナル(NLS)
真核細胞ではDNAは核膜に包まれており、Cas9が働くには核の中に入る必要があります。ここで使われるのが核局在化シグナル(NLS: nuclear localization signal)です。
・NLSは特定の短いアミノ酸配列(例:SV40由来のPKKKRKV)で、細胞の輸送機構がそれを認識してタンパク質を核内に運びます。
・GFPや転写因子を核に送り込むためにNLSを付加するのは、分子生物学実験ではごく一般的な手法です。
Cas9にNLSという「免状」が付いていなければ、核膜の「ゲートの内側」に入ることができず、Cas9は目的地までたどり着くことができません。原告はこの点についても指摘していました。
しかし、2012年当時、Cas9のように核で働かせたいタンパク質にNLSを付けるのは「特別な発明」ではなく、「当業者が当然に選択する調整」として認識されていました。裁判所もこの点を重視し、「真核細胞での適用にNLSの付加は慣用技術」と判断しました。
3.コドン最適化
DNAは3塩基(コドン)ごとにアミノ酸を指定しますが、同じアミノ酸でも複数のコドンがあります。そして、どのコドンを好んで使うかは生物種によって異なります。
・大腸菌でよく使われるコドンと、ヒト細胞で好まれるコドンは違います。
・そのため、大腸菌由来のCas9遺伝子をそのままヒト細胞に導入すると、タンパク質がうまく作られないことがあります。
・そこで、アミノ酸配列はそのままに、ヒトの細胞が好むコドンに置き換える「コドン最適化」を行います。
コドン最適化の概念を説明するのによく例えられるのは、「方言」です。ある地域(大腸菌)の方言を使って別の地域(ヒト細胞)で指令を出しても上手く通じないため、方言を正す(コドン最適化)処理が必要になります。この点も原告は指摘していました。
しかし、2012年当時、コドン最適化はすでに標準技術であり、オンラインで自動設計できる商用ツールもありました。判決では「Cas9を真核細胞で発現させるためのコドン最適化は当時の周知技術」と評価されました。
4.これら3つがなぜ判決で重要だったのか?
原告は「真核細胞での適用に必須の技術が明示されていない」と主張しました。しかし裁判所は、第1出願書類の記載と当時の技術常識を総合すれば、当業者はこれらの要素を組み合わせて過度の試行錯誤なくCRISPR/Cas9を真核細胞で実施できたと判断しました。
・PAM配列は「切断の必須条件」として認識されていた
・NLSの付加は核内タンパク質で一般的な調整
・コドン最適化は異種細胞で発現させる際の標準的手法
この3つの“当たり前”の技術が、2012年5月25日の優先権を守る鍵となったのです。
次回予告
第3部では、CRISPR/Cas9の土台となったZFNやTALENといった先行技術、そして哺乳類細胞での編集を可能にした発現ベクターやトランスフェクションといった基盤技術を解説します。CRISPRが「突然の革命」ではなく、積み上げられた技術史の延長線上にあることが見えてきます。