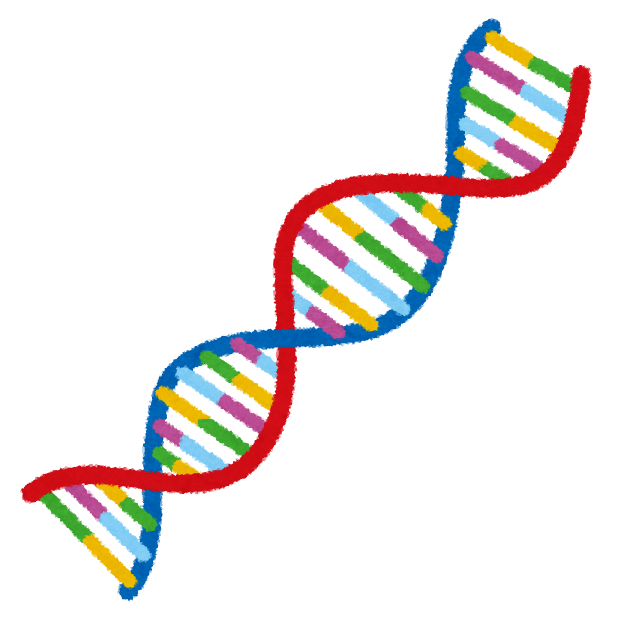前回の記事(「アメリカで承認された「遺伝子編集ナタネ」—その意味と、日本への影響とは?」)で、CRISPR-Cas9(クリスパー・キャスナイン)という技術について言及したため、今回はこのCRISPR-Cas9の仕組みと、農業への応用例、そしてそれが乗り越えてきた技術的課題についてご紹介します。
1.CRISPR-Cas9とは?―細菌の防衛機構から生まれた技術
CRISPR-Cas9は、もともと細菌がウイルスの侵入に対抗する仕組みを応用した技術です。細菌は過去に侵入してきたウイルスのDNAの一部を「記録」しておき、再び同じウイルスが来たときに素早く撃退できるようにしています。この記録こそが、CRISPR配列です。
2.CRISPR配列とは?
CRISPR配列(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)は、ウイルス由来のDNA断片(スペーサー)と、一定の繰り返し配列(リピート)から構成されます。これをもとに細菌は「ガイドRNA(gRNA)」を作り、侵入したウイルスのDNAを認識・攻撃します。
3.Cas9酵素とgRNAの関係
・gRNA(ガイドRNA):ウイルスや標的遺伝子を正確に見つけ出す“ナビゲーター”の役割を担います。
・Cas9酵素:gRNAに導かれ、目的の場所に到達するとDNAを切断する“分子のハサミ”です。
この仕組みを例えるなら、
ウイルス=ドロボウ、gRNA=手配写真、Cas9酵素=警察官と考えると分かりやすいでしょう。
ドロボウ(ウイルス)が細菌の中に侵入すると、その姿が写真に撮られ(gRNAに記録され)、全国の交番(細胞内)にその手配写真が配られます。警察官(Cas9酵素)はその写真を頼りにドロボウを見つけ出し、確実に捕まえる(DNAを切断する)のです。
この2つ(gRNAとCas9酵素)を人工的に組み合わせることで、以下のような機能を実現できます。
(1)特定の遺伝子を正確に狙い、
(2)その遺伝子を切断し、
(3)突然変異を引き起こす。
この一連の流れが、CRISPR-Cas9システムの基本的なプロセスです。
4.農作物への応用例
こうした技術はすでに農作物の改良に応用されています。例えば、トマトではRIN遺伝子(Ripening-inhibitor)を標的にCRISPR-Cas9を用いて変異を導入することで、熟成をコントロールし、収穫後の日持ちを大きく改善することに成功しました。
これは、(1)gRNAでgRNAでRIN遺伝子の一部を標的にし、(2)Cas9酵素でDNAを切断、(3)細胞の修復過程で意図的な変異を起こさせるというステップを踏んで行われました。
また、イネでは細菌性病害であるいもち病への耐性強化が試みられています。特に注目されているのがOsSWEET遺伝子群の編集です。
これらの遺伝子は病原菌が感染の際に利用する“入り口”のような役割を持つため、特定のSWEET遺伝子のプロモーター領域を編集することで、病原菌の侵入を防ぎ、耐病性を高めることができます。これも、(1)gRNAの配列設計と(2)Cas9による切断、そして(3)変異誘導というステップを踏むことで実現されています。
5.CRISPRが乗り越えた技術的課題
遺伝子編集技術が登場する前の「遺伝子組換え技術」には、いくつかの課題がありました。
| 従来の課題 | CRISPRでの解決 |
|---|---|
| 他生物の遺伝子を導入する必要があった | 自己の遺伝子を改変するだけでOK |
| 狙った場所だけを改変するのが難しい | gRNAでピンポイント編集が可能に |
| コスト・時間がかかる | 短期間・低コストで実施可能 |
さらに、CRISPRでは外来遺伝子を組み込まずに既存の遺伝子を改変できるため、自然交配や突然変異による品種改良と同等に扱う国も増えています。日本でも、外来の遺伝子を導入せず、既存の遺伝子配列を改変するだけ(いわゆる「SDN1型編集」)であれば、遺伝子組換え作物(GMO)には該当せず、食品表示の義務対象外*とされています。
*関係省庁への所定の届出を経て確認される必要があります。(最新の詳細情報は各自でご確認ください。)
6.オフターゲット変異とその対策
CRISPR-Cas9は非常に強力な遺伝子編集ツールですが、その課題のひとつに「オフターゲット変異」があります。これは、gRNAが標的に似た別のDNA配列と誤って結合し、意図しない場所でDNAを切断してしまう現象です。
(先ほどの例えで言えば、正しい手配写真をもとに動いていたにもかかわらず、警察官が写真と“よく似た別人”を誤って逮捕してしまうようなものです。)
この問題に対処するため、現在では高い精度で標的を認識するCas9酵素(例:HiFi Cas9やeSpCas9など)が開発されています。これらは非標的領域への結合を抑えるよう設計されており、オフターゲットのリスクを大きく低減できます。
さらに近年では、AIやゲノムデータベースを活用して、あらかじめオフターゲットの可能性がある配列を予測し、それを避けるようにgRNAを最適設計する手法も広く利用されています。
7.おわりに:CRISPRは未来の農業の「ハサミと編集ツール」
CRISPR-Cas9は、遺伝子を正確に切る「ハサミ」であり、書き換える「編集ツール」として、未来の農業に大きな可能性をもたらしています。気候変動に強い作物や、アレルゲンの少ない食品など、私たちの食と健康をより豊かに支える応用がこれから広がっていくでしょう。
自然の力と調和しながら、持続可能で実りある農業を築く。その挑戦を後押しする鍵のひとつが、CRISPRという技術なのです。
出典:農林水産技術会議HP 「ゲノム編集~新しい育種技術~」
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/genome_editing_leaflet/genome_editing_leaflet.html#interview_1-3