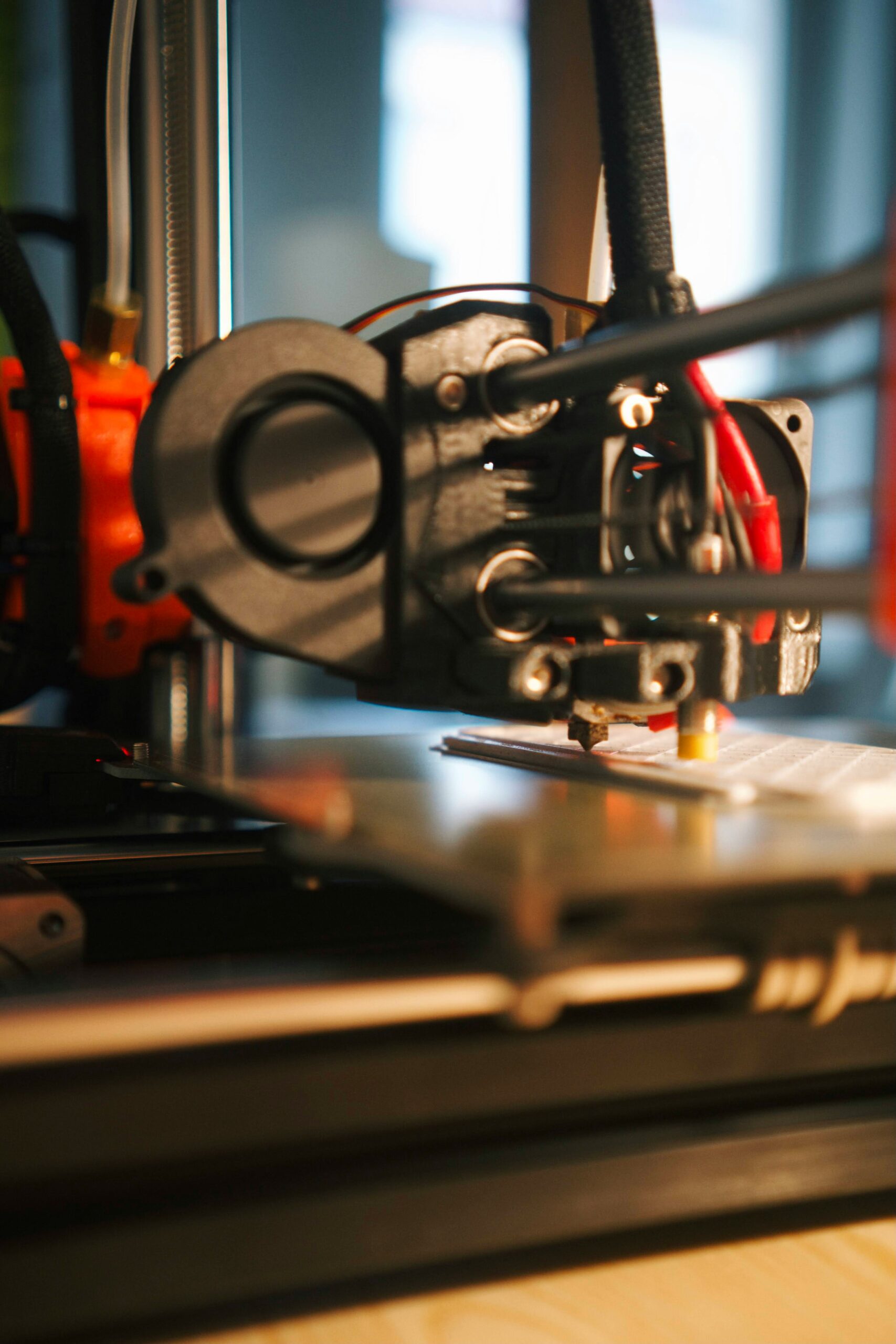2025年現在、世界の食品業界で「機能性食品(Functional Foods)」は大きな注目を集めています。機能性食品は、栄養補給や美味しさだけでなく、単なる栄養価を超えて健康維持や生活の質向上に寄与すると考えられる成分を含む食品のことを指します。この記事では、なぜ機能性食品が一過性のブームではなく今後も継続すると考えられるのか、そして日本発のどのような機能性食品が世界市場で成功する可能性があるのかを整理してみます。
1.機能性食品は一過性の流行ではない
ダイエット法や「スーパーフード」の一部は、短期間で消えていくことが多いですよね。しかし、機能性食品はそのような一過性のブームとは性質が異なります。理由は大きく3つあります。
(1)健康志向の定着
世界的に高齢化や生活習慣病の増加が進んでおり、「食で予防する」という意識は年々強まっています。これは一時的な流行ではなく、社会構造の変化に根差した動きです。
(2)医療費抑制のニーズ
欧米や日本では医療費が増え続けており、予防医療の重要性が増しています。サプリや薬に頼る前に「毎日の食事で健康を維持する」ことが、国や企業レベルでも推奨されつつあります。
出典1:国際連合公式HP
https://www.un.org/en/global-issues/ageing?utm_source=chatgpt.com
出典2:OECD公式HP
https://www.oecd.org/en/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239/full-report/health-expenditure-in-relation-to-gdp_e3566919.html?utm_source=chatgpt.com
(3)機能性の“当たり前化”
かつては「健康志向の一部の人が選ぶ」ものでしたが、現在は多くの消費者が「飲料やスナックに健康メリットがあるのは当然」と考えています。例えば腸活ヨーグルトやプロテイン入りスナックなどは、すでに一般市場に深く浸透しています。
このように、機能性食品は今後も継続的に成長していくと予想されます。
2.日本発で世界的ヒットの可能性がある分野
では、日本の伝統や食文化から生まれた食品の中で、どんなものが世界で成功する可能性が高いのでしょうか。いくつか注目すべきジャンルを紹介します。
(1)発酵食品 × プロバイオティクス
納豆、味噌、漬物、醤油など、日本は「発酵文化」の宝庫です。これらは腸内フローラを整える可能性が期待されており、すでに世界的に注目されています。例えば、乳製品を避ける人には植物性のプロバイオティクス*が大きな魅力となります。また、ヤクルトのような商品は、臨床データと伝統を組み合わせることで世界展開に成功しています。
*「プロバイオティクス」の健康表示(health claim)はEUでは承認されておらず、食品ラベルに『プロバイオティクス』と記載する際には表現可能な範囲に注意が必要です。
出典3:アイルランド食品安全庁
https://www.fsai.ie/business-advice/nutrition/probiotic-health-claims?utm_source=chatgpt.com
(2)緑茶・抹茶
抹茶はすでに「ヘルシードリンク」として世界中に広まっていますが、その機能性はまだ十分に伝えきれていません。抹茶に含まれるL-テアニンは、一部の臨床研究においてリラックス作用や注意力維持への寄与が示唆されており、カフェインと組み合わせることで「集中しつつ落ち着ける」というユニークな効果を持ちます。これを科学的に裏付けて打ち出せば、エナジードリンクやカフェインサプリの代替品としてさらに拡大が期待できます。
(3)海藻食品
海藻は低カロリーでミネラル・食物繊維が豊富であるのに加えて、環境負荷が小さく、サステナブル食材としても注目されています。例えば海藻スナックや海藻由来の食物繊維を配合した商品は、健康と環境の両面から訴求でき、欧米市場で強い需要が見込まれます。
(4)ナットウキナーゼや黒酢などの伝統素材
納豆に含まれるナットウキナーゼは、血栓溶解作用に関する基礎研究や限定的な臨床研究が存在し、心血管系の健康サポート素材として注目されています。また、黒酢や梅干し、柚子なども「免疫サポート」や「疲労回復」といった分野で訴求可能です。ここでも重要なのは「日本の伝統 × 科学的エビデンス」という組み合わせです。
3.世界市場で戦うための戦略
ただし、「良い素材がある」だけでは成功できません。グローバル市場で日本発機能性食品を広めるためには、以下の戦略が必要です。
(1)科学的エビデンスの確保
消費者や規制当局を納得させるには、ヒト臨床試験のデータが欠かせません。例えば「腸内環境の改善」や「集中力アップ」といった効果を明確に示す小規模臨床試験を行うことで、商品の信頼性が大きく高まります。
(2)法規制に対応した表示
国ごとに「健康効果」をどう表現できるかが異なります。例えば、米国では比較的柔軟に「◯◯をサポート」と表記することが可能(ただし真実性・根拠が必要であり、疾病クレームは不可)ですが、EUは事前承認制で、科学的裏付けが厳格に求められます。このため、現地のルールに合わせたラベル設計が不可欠です。
出典4:欧州食品安全機関
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/health-claims?utm_source=chatgpt.com
(3)ブランディングとストーリーテリング
「日本の伝統」「科学的根拠」「現代的な便利さ」をストーリー化して伝えることが重要です。例えば「京都産の抹茶を使い、科学的に効果が検証されたリラックスドリンク」といった形で、文化と科学の両方を訴求できます。
(4)販売チャネル戦略
初期段階ではD2C(自社ECサイトやAmazon)でブランドを育て、その後は現地の健康食品ショップやカフェチェーンとの提携に広げるのが現実的です。抹茶ドリンクがスターバックスなど大手カフェチェーンと組むことで一気に拡大した事例も参考になります。
(5)供給リスクへの対応
例えば、抹茶や海藻は需要拡大で価格や供給が不安定になるリスクがあります。長期契約や複数の産地からの調達で安定供給を確保することも戦略の一部になります。
4.今後の展望とまとめ
機能性食品は「一部の流行」ではなく、世界的に定着する大きな潮流です。その背景には高齢化や医療費増大、そして消費者の健康志向という根本的な要因があります。特に日本発の食品は、発酵文化や茶文化といった「伝統」と、臨床データや科学的根拠といった「信頼性」を組み合わせることで、世界市場で大きな成功を収める可能性を秘めています。
今後、日本企業やスタートアップがやるべきことは、単に「伝統的で健康に良い食材を輸出する」ことではなく、エビデンスと現地適応型のブランディングをセットにした形で展開することです。そうすれば「抹茶=おしゃれな健康飲料」や「納豆菌=腸活の新定番」のように、日本発の機能性食品が世界の食文化の一部になる未来も十分にありえるでしょう。
補足:世界の食品業界全体の動向については、FoodNavigatorのレポート『Food and Beverage Trends 2025』も参考になります。機能性食品だけでなく、スナックの成長やアルコール消費の減少など、幅広いトレンドが整理されています。
出典5:Food and Beverage Trends 2025
https://www.foodnavigator.com/Article/2025/08/22/food-and-beverage-trends-2025-whats-hot-and-whats-not/